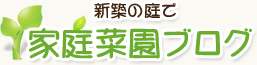
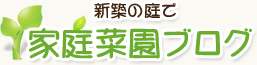
お庭の手入れをした時、DIYで花壇を作ったとき、家庭菜園の土の入れ替えをしたりなど、様々な状況で「残土」というものが発生することがあります。
しかし土は、自治体などが収集する家庭ゴミとしては扱えないことが多く、また直接焼却場などに持ち込んでも処理はしてくれません。
唯一、民間のゴミ処理業者に持ち込むことが可能ですが、45リットルの袋、一袋あたり2000円~3000円も費用がかかってしまいます。
土を捨てるということが意外にも難しいことがお分かりいただけるかと思います。
そこで今回は、余った土を捨てようと考えるのではなく、「腐葉土にして再利用」することに挑戦してみました。
残土を腐葉土にする方法は後ほどご紹介しますが、腐葉土を作り終えるまでには期間として半年から1年程度必要となります。
つまりそれだけの期間、残土を置いておく場所が必要となる訳ですが、一般住宅や建売住宅では土を広げて置いておくスペースなんてあまりないと思います。
そこで、まずは腐葉土を作るための「残土ボックス」の制作から始めました。
用意したものはこちら。

ホームセンターで手に入るコンパネ。
もしくは大きいベニヤ板でもいいかもしれません。
この合板をのこぎりで切るのは難しいので、ホームセンターにて横板4枚、底板1枚のサイズを指定して切ってもらいました。
家具を作る訳ではないので、大きさもだいたいで大丈夫です。
次にこの残土ボックスは屋外に設置するものとなりますから、当然雨風にさらされてしまいます。
このままの状態で置いておいては木が腐ってしまいますので、外側にあたる面だけ防腐剤を塗っておきましょう。
使用したのは防腐剤で有名なキシラデコール。

一般的な塗料のように塗膜を作るのではなく、木に浸透して雨水の浸入や腐食を防いでくれます。

2~3時間ほど乾かしたら、組み立て工程へ。

ビスを使って四角く組み立てていきます。

木にビス打ちする際は、必ず下穴を作ってからビスを打ち込みましょう。

こうすると、ビスを入れた時に木が割れにくいです。
あっという間に完成。

女性でも簡単に出来ると思います。
この残土ボックスは、畳約0.5畳分の広さですが、MAXで45リットル袋10杯程度の土が入ります。
さらに省スペースなので、家の裏側など目立たないところに設置することができ、見栄えを気にする必要がありません。
もっと大きさや容量が必要ならボックス自体を大きくしても問題ありませんが、腐葉土を作る過程で「かき混ぜる」という工程が必要となりますので、大きいとやりにくいかもしれません。
大きくするよりは2個3個と増やした方が効率的かと思います。
残土ボックスができたら、腐葉土作りに入りましょう。
時期としては、枯れた落ち葉が集まりやすい秋~剪定枝の集まる冬がベストです。
まずは残土ボックスに残土を入れ、高さが20~30cmくらいになったところで一度止めます。

ここへ、庭にある落ち葉などをかき集めて敷き詰めます。

この上にもう一度残土を入れていき、今度も20~30cmくらいの高さで止めます。
再度落ち葉や枯れ葉を入れて、土と枯れ葉でミルフィーユ状にしていきます。
これを繰り返すだけでも腐葉土を作ることはできるのですが、発酵を早めるため、生ゴミ処理機があればそのカスを入れたり、米ぬかなどを入れても発酵を助けてくれます。
これらが無ければ、純粋な腐葉土(培養土などの混ざった物ではなく)を買ってきて、落ち葉を入れる時に腐葉土を混ぜることでも発酵は促進されやすくなります。

ご近所のことを考えて、未処理の生ゴミや、魚の骨などを入れるのは避けましょう。
冬の時期ならば、庭に生えている木の剪定枝や枯れ枝を入れても堆肥になります。

特に木の皮を入れた堆肥はバーク堆肥としても有名ですね。
多少濡らしてから投入すると、発酵が早いです。
さらに手軽さを求めるのであれば、「土のリサイクル材」を入れることをお勧めします。
バーク堆肥をベースに、有効微生物を混ぜた商品で、発酵を促進します。
これらを残土とサンドして入れ終えたら、雨水が入らない様に防水シートなどで覆っておきます。

ただ覆うだけでは風で飛ばされてしまうので、一部を残土ボックスに固定してしまっても良いと思います。

これで腐葉土を作る準備が整いました。
土を入れた日から2ヶ月程度を目途に、1度全体をかき混ぜましょう。
量が沢山あるようなら、上の方の土を一度バケツやポリ袋に取り出して、下の方からかき混ぜていきます。
少し黒くなってきていれば発酵が進んでいる証。
この後は1ヶ月に1回程度混ぜていきましょう。
全体が黒くなり、フカフカしてきてきたら、残土から腐葉土の完成。
冬に腐葉土を作りはじめたら、翌年の春に畑へすき込むと、調度良い仕上がりになっていると思います。
 東京都在住。
東京都在住。